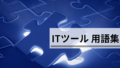Mentionを知らない方にもわかりやすくまとめた記事です。SNSやWeb上でのブランドや自社の評判を監視・分析したい方に向けて、Mentionの仕組みや活用法を丁寧にご紹介します。
Table of Contents
Mentionとは?
Mentionは、インターネット上で特定のキーワードが言及された情報をリアルタイムで収集・分析できるツールです。主にSNS、ニュース、ブログなどを対象に監視し、ブランドモニタリングや競合分析に活用されます。自社に関する言及をいち早く察知できるため、評判管理や危機対応にも役立ちます。
わかりやすい具体的な例
わかりやすい具体的な例1
たとえば、カフェを経営している場合、Mentionで「カフェ店名」や「店の最寄り駅 カフェ」などのキーワードを登録すると、誰かがSNSでその店を話題にした投稿が通知されます。これにより、お客様の声を即座に把握し、返信やサービス改善につなげることができます。
この図では、Mentionがユーザー投稿から該当キーワードを検出し、即座に管理者へアラートを送信し、対応へとつなげる流れを示しています。
わかりやすい具体的な例2
企業が新商品を発表した直後、Mentionでその製品名をモニタリングしておくと、メディアや一般ユーザーのリアルな反応がすぐに把握できます。これにより、商品に対する期待・不満の傾向を見極め、次の戦略に活かすことが可能です。
このフローでは、新製品に関する投稿がMentionによって収集され、感情分析や改善点の抽出に活かされていることがわかります。
Mentionはどのように考案されたのか
Mentionは、SNSの発展により情報の拡散が瞬時に行われる時代に対応すべく、フランスで誕生しました。従来のGoogleアラートに代わるリアルタイムモニタリングツールとして開発され、複数メディアの横断検索と、可視化された分析機能を組み合わせて企業のレピュテーション管理を強化しました。
考案した人の紹介
Mentionは、フランスの起業家Arnaud Le Blanc氏とAntoine Richomme氏によって2012年に考案されました。Le Blanc氏は、Webアプリ開発とデータマイニングに精通しており、情報の即時性が求められるSNS時代に応えるツールを目指して開発を進めました。彼らはリスニング技術に注目し、視覚的に操作できるUIと、ユーザーに届きやすい通知設計を同時に取り入れました。
考案された背景
当時のWebマーケティング分野では、企業のブランドイメージ管理においてSNS監視が十分にできていないという課題が顕在化していました。Mentionはこのニーズに応える形で、リアルタイム性と網羅性を備えた新たな監視・分析ツールとして登場しました。
Mentionを学ぶ上でつまづくポイント
Mentionを使い始めた多くの方が戸惑うのは、「どのキーワードを登録すればよいか」という点です。たとえば、自社名だけでなく、商品名、業界名、競合名も併せて登録することで効果的に情報を集められます。また、「ノイズの多さ」もよくある課題です。これはフィルター機能で除外ワードや地域を設定することで軽減できます。ツールに慣れるまで、ダッシュボードの使い方に時間がかかることもあるため、初期チュートリアルを活用するとよいでしょう。
Mentionの構造
Mentionは、クローラーが複数のオンラインメディアを巡回し、事前に登録されたキーワードに基づいて情報を収集します。これをリアルタイムで解析し、感情分析やエンゲージメント指標と共にダッシュボードへ可視化します。AIによる分類処理と通知設計が連動することで、ユーザーは素早く重要な情報にアクセスできます。
Mentionを利用する場面
Mentionは、企業の評判管理や、マーケティング戦略の補完として活用されることが多いです。
利用するケース1
たとえば、広報部門では製品のネガティブレビューをいち早く検知する必要があります。Mentionはその点で、批判的な投稿を自動で感知し、該当部署に通知する機能を提供しています。これにより、迅速な対応や危機管理体制の構築が可能になります。特に炎上の初期段階で情報を察知できれば、ブランド価値の低下を最小限に抑えることができます。
利用するケース2
スタートアップ企業では、Mentionを用いて投資家や業界メディアに言及された回数を分析し、認知度の向上状況を可視化するケースがあります。Mentionのレポート機能を活用すれば、週ごとの言及数や反応のトレンドを把握することができ、プレゼン資料や事業報告にも活用可能です。
さらに賢くなる豆知識
Mentionには「Booleanクエリ」を用いた高度な検索機能があります。これは、AND、OR、NOTなどの演算子を活用して複雑な条件でのモニタリングを可能にする機能です。また、MentionはSlackやメールと連携できるため、通知の受信先を柔軟に変更することができ、社内チームでの共有もスムーズに行えます。
あわせてこれも押さえよう!
Mentionの理解を深めるには、同様の用途や補完的な機能を持つ他のツールについても知っておくとより効果的です。
- Hootsuite
- Brand24
- Sprout Social
- BuzzSumo
- Googleアラート
複数のSNSを一括管理できるダッシュボード型ツールで、投稿スケジュールの自動化が可能です。
Mentionと似たリアルタイムモニタリングツールで、詳細な分析レポートも特徴です。
ソーシャルCRMや顧客対応に優れており、チームでの活用がしやすい設計です。
コンテンツマーケティング向けに、人気記事や話題のトピックを抽出できます。
無料で使える情報監視ツールですが、Mentionに比べて即時性や分析力はやや劣ります。
まとめ
Mentionを活用することで、企業やブランドの評判をリアルタイムで把握し、柔軟な対応や戦略立案に活かすことができます。使い方に慣れれば、チーム全体での情報共有もスムーズになり、マーケティングの強化にもつながります。情報社会におけるリスク管理と機会創出の両面で、非常に役立つツールです。