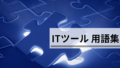Feedlyをまだ知らない方のために、このツールの基本的な使い方から活用法までをわかりやすく解説します。情報収集に役立つ便利なツールを探している方にぴったりの内容です。
Table of Contents
Feedlyとは?
Feedlyとは、複数のニュースサイトやブログの更新情報を一元的にチェックできるRSSリーダーです。気になる情報源を登録することで、最新記事を一覧形式で確認できます。スマートフォンやパソコンなど、どのデバイスでもアクセス可能で、効率的な情報収集が可能になります。
わかりやすい具体的な例
わかりやすい具体的な例1
たとえば、料理が趣味の方が「クックパッド」「E・レシピ」など複数のレシピサイトを巡回していたとします。Feedlyを使えば、それらのサイトの新着レシピをまとめて一画面で確認でき、わざわざ各サイトを訪問する必要がなくなります。毎日の情報収集が時短できるのです。
Feedlyにレシピサイトを登録しておけば、更新された内容だけが自動的に一覧表示されます。記事を探す手間を省けるため、日々の料理のヒントを効率よく得ることができます。
わかりやすい具体的な例2
たとえば、就職活動中の学生が企業の採用ブログやキャリア系のニュースサイトを日々チェックしている場合、Feedlyを使えばそれらを一括で管理できます。時間をかけずに新着情報を拾い上げられるため、情報収集に漏れがありません。
複数企業のブログを1つのアプリで確認できるため、チェック漏れを防ぎつつ、効率よく就活に役立てることができます。
Feedlyはどのように考案されたのか
Feedlyは2013年にGoogle Readerの終了を受けて、多くのRSSユーザーが代替手段を求めていた時期に登場しました。もともとは米国のスタートアップ企業が開発したアプリであり、Google Readerに代わるサービスとして急速に支持を集めました。RSSという技術を使って、誰でも簡単に情報収集ができるように設計された点が評価され、現在では個人利用からビジネス利用まで幅広く使われています。
考案した人の紹介
Feedlyを開発したのは、フランス出身のEdwin Khodabakchian(エドウィン・コダバキアン)氏です。彼はかつてNetscapeやOracleに勤めていた経験があり、情報技術に精通したエンジニアとして知られています。情報の洪水に悩まされる現代において、ユーザーが効率よくコンテンツを選別できる方法を模索する中で、RSS技術に着目し、Feedlyを開発しました。
考案された背景
インターネット上に情報が爆発的に増える中で、効率的な情報収集の手段が求められていました。Google Readerの終了により、RSSリーダーの空白が生まれたことが契機となり、Feedlyは登場しました。RSSの可能性を活かし、専門家や一般ユーザーにとっても有益な情報管理ツールとして普及したのです。
Feedlyを学ぶ上でつまづくポイント
Feedlyを初めて使う人がよく戸惑うのは、「RSSって何?」という点です。RSSは「Really Simple Syndication」の略で、情報配信の仕組みですが、普段使わない用語のため理解が難しく感じられるのです。また、購読の仕組みやフォルダの分類など、最初は設定の仕方で混乱しがちです。しかし一度仕組みを理解すれば、GoogleアラートやPocketなどのサービスと併用して、より便利な使い方が可能になります。
Feedlyの構造
Feedlyは、RSSフィードを収集し、ユーザーがカスタマイズしたフォルダやタグを用いて記事を整理する構造になっています。記事は「未読」「既読」「保存」などの状態で管理され、視覚的に整理されたインターフェースで一覧表示されます。また、Feedly Proなどの有料プランでは、AIによる記事の優先順位付け機能も利用できます。
Feedlyを利用する場面
ニュース収集や業界動向の把握など、日常の情報整理に役立ちます。
利用するケース1
マーケティング担当者が競合他社のブログや業界ニュースを毎日チェックする必要がある場合、Feedlyを使えば一括で確認できます。複数のメディアをまたいで情報を効率よく収集できるため、毎朝のルーチンが簡素化されます。また、気になる記事を保存して後から分析することも可能です。
利用するケース2
研究者が特定の学術ジャーナルや技術系ブログを定期的にチェックする際にもFeedlyが有効です。毎回検索する必要がなく、関心のあるトピックのみを自動でまとめてくれるため、研究の効率が大幅に向上します。
さらに賢くなる豆知識
Feedlyには、AI機能「Leo(レオ)」があります。これは自分の関心に合った記事を自動で優先表示してくれるスマート機能です。また、IFTTTやZapierと連携すれば、記事の自動保存やSlack通知などの自動化も可能です。さらに、Googleキーワードアラートと組み合わせることで、リアルタイムでの情報把握にも役立ちます。
あわせてこれも押さえよう!
Feedlyの理解を深めるためには、以下のツールや概念もあわせて学ぶと効果的です。
- RSS
- Google アラート
- IFTTT
- Zapier
情報配信の仕組みで、Feedlyの根幹を成す技術です。Webサイトの更新情報を自動取得する手段として活用されます。
キーワードに基づいた新着情報をメールで通知してくれるGoogleの無料サービスです。Feedlyと併用すれば情報漏れが減ります。
後で読みたい記事を保存しておけるツールです。Feedlyと連携すればワンタップで保存可能です。
Feedlyで読んだ記事を自動的にGoogle スプレッドシートに保存するなどの自動化が可能なサービスです。
さまざまなWebサービスを連携させる自動化ツールで、Feedlyとの連携により高度なワークフローが作成できます。
まとめ
Feedlyを活用することで、毎日の情報収集が劇的に効率化されます。ニュースやブログのチェックが簡単になり、仕事や趣味の情報収集の質が高まります。使いこなせば、現代の情報社会をスマートに生き抜く武器となるでしょう。